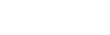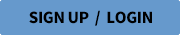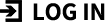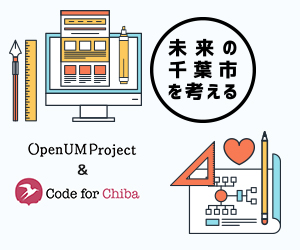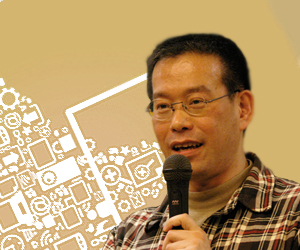取材・構成
昨年から盛り上がってきたスマートフォンの普及は、2011年に入り一層加速してきており出荷台数ベースでは、2011年度が前年比2.3倍の1,986万台、携帯電話の総出荷台数の49.0%を占めると予測されている(*)。既にYahoo!JAPAN、Googleといった検索サイト、さらにメディアなど多くのサイトがスマートフォン専用サイトを準備(以下、スマートフォン対応)している現状から、企業のWeb担当者は、PCサイト、携帯サイトに加え、スマートフォン対応を、否が応でも意識し始めているだろう。しかし、何を考え、どこから手をつければ良いのか?と、いきなり迷ってしまう…。
そこで、ウェブエキスパート編集部では、Web制作全般に関するトピックを取り上げるセミナーイベント『CSS Nite』の常連ゲストスピーカーであり、書籍『iPhone+Android スマートフォンサイト制作入門 (WEB PROFESSIONAL)』などの執筆で知られる、エイチツーオー・スペースのたにぐちまこと氏に、賢くスマートフォン対応するための心掛けを伺った。多くのスマートフォンサイト制作を手掛ける氏の経験をもとに、Web担当者が知っておくべきことを10のポイントで紹介していこう。
聞き手:小野村香里(株式会社ロフトワーク/システムDiv.)
(Webエキスパートより転載)
*『スマートフォン市場規模の推移・予測(11年7月)』 (株) MM総研 [ 東京・港 ] より
スマートフォン対応の前準備が、サイトの出来を左右する
「急速にスマートフォンが普及する現在、いろんなお客様を見ていると、ポジティブにスマートフォンに対応される企業と、ネガティブに対応される企業に分かれてきていますね」と、たにぐち氏は企業のスマートフォン対応の現状について語る。
2つの対応は、例えば「風邪をひかない体になるためにジムへ行く」と、「風邪をひいてしまって病院に行く」くらいの違いである。
ポジティブな対応としては、現状の企業サイトがPCユーザーのみにターゲティングされているが、マーケティング解析・アクセス解析等の結果からスマートフォン対応でアクセス増が見込まれるため、対応するという具合。一方、ネガティブな対応は、自社のサービスが “携帯サイト“の月額課金モデルに依存しており、現在のスマートフォンの急速な普及によってユーザー離れが加速し、収益が急落したので急いで対応するといった具合である。
「今年の夏は、まさに“スマートフォンの夏”でしょうね。初夏からのスマートフォンの普及はすごい勢いで進んでいます。自社サイトをスマートフォン対応させるのであれば、“どういうサイトを目指すか?”を早めに判断しなければなりません。目的を明確にして、結果としてサービスの受け手から見ても分かりやすく使いやすいサービスすることが重要ですね」
ポジティブな対応を行う企業にとってはチャンスであり、ネガティブな対応になりそうな企業は、改めて方針を決めておく必要がある。今年の夏はまさにその分岐点と言ってもいいタイミングなのである。
ポイント1 現時点で、すでにスマートフォン対応に何らかの答えが出せている
たにぐち氏が案件を受注する際によく直面するのは、予算への誤解だという。スマートフォンサイトは画面も小さいし、デザインもシンプルなものが多いため、PCサイトよりも工数が少なく簡単にできるイメージを持たれがち。ここが落とし穴となると指摘する。
「例えば、Yahoo!JAPANのスマートフォンサイトを見てみましょう。あれだけ小さな画面で、タブで画面を切り替えることができたり、画像がカルーセルできたり、パネルが下部から出てきたりと、ユーザーインターフェースに様々な工夫がこらされていますね。このような場合、スマートフォンサイトがPCサイトよりも制作工数がかかるということも珍しくありません。まずは、PCサイトをスマートフォンサイトに置き換える発想でなく新たに違うUI(ユーザーインターフェース)を持つサイトを制作すると理解すること、さらに、リニューアル担当者であれば、その考えを周囲に理解してもらうことが大切ですね」

Yahoo!JAPANのスマートフォンサイト(iPhoneでの表示) 国内サイトでは早い時期からiPhone対応していたことで知られる。タブ、スクロール、スライダー、プルダウンメニューを適材適所で配備し、 ニュース、ショッピング、オークションなどPCサイトと同様の機能をまんべんなく提供している
サイト構築に当たり、社内の予算検討の際に上記のような前提を置けているかは重要だ。予算が少ない場合、結果としてスマートフォンサイトの完成度を左右しかねない。スマートフォンサイトは“オマケ”感覚ではなく、ひとつのWebサイトを作るものと考えた方が良さそうだ。
ポイント2 スマートフォンサイトの特性をフル活用したい場合、構築予算を十分に確保する