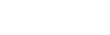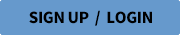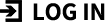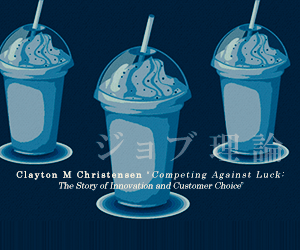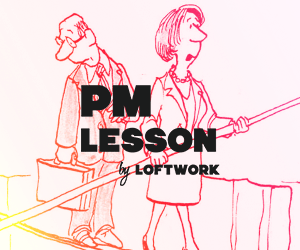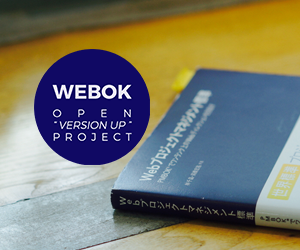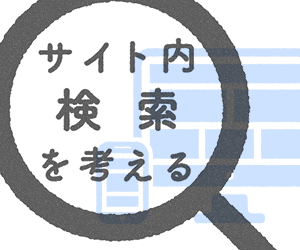自律的なWebチーム構想は、会社での立場の保証と、能動的な状況把握の促進から
チーム全体の構成が話の中心だった前半に対し、後編は評価や個性の生かし方など個人についての話である。一般的には、自社のWebサイトに関する具体的な指示が経営層から直接Webチームに降りてくることは稀。指示がある場合、方針や大体のイメージでの指示となるだろう。上からの意見に漫然と従っていることで、単純なルーティンワークに陥りがちとなり、 “やらされ感”も出てくる。それらの解消法として増井氏が行っている試みはとてもユニークなものだ。
「ウェブマネジメントセンター所長になってからすぐに、社内規程の中にインターネットを利用した情報の発信と収集の基本規程を作りました。そして、Webチームが“グループ全社のWebガバナンスに責任を持つ部署である”と明記することで、義務と責任を明確化したんです。このような規程を自ら作り、下請け的な部署ではなく自律的な行動・発現ができる環境を整備することにしました」
社内での立場を確立しておくと、後々、他事業部とやり取りを行う場合、組織間の上下関係が生まれにくくなる。それぞれの責任で対等に話し合いができるというものだ。
- 工夫その6 Webチームの責任と義務を明確化することで、自律した存在となる
さらに増井氏は、メンバーの一体感を高めるために、チームの仕事がいかに会社全体のミッション・ビジョンに基づいているかを明確化する工夫をしている。例えて言うなら、チーム全員をバスの常客だとしたとき、運転手がなぜハンドルを切ったかということを、全員が即座に分かるようにしているのだ。目の前に起こっていることに“それは会社の決めたことだから”で振り回されるチームではなく、“こういった理屈があるため必然のことだ”と能動的に解釈できることが、自律的なWebチームにとって必要なのだ。
「グループ全体のミッション・ビジョン、その長期経営構想、中期経営計画、コミュニケーション本部のミッション・ビジョン、そしてウェブマネジメントセンターの部門目標、チームの仕事(SE、ディレクター、デザイナーなど)の関連を1枚のシートにまとめています。これが末端のチームに共有されることで、提供すべき価値を前提とした仕事か、あるべき姿にきちんと向かっているかなどを個々が判断できるわけです。そして、仕事に自信を持つことができます」

キヤノンマーケティングジャパンで使用されているビジョンの関連性を一覧できるドキュメント(サンプルイメージ)。 最下部は各個人が記載することになる
チーム内でのそれぞれの仕事がきちんと会社の目標に繋がっているというのが常に一覽でき、認識される体制を構築することは、モチベーションの向上に一役買っている。
工夫その7 会社の仕事とチームの仕事の関連性を常に明確化し、“やらされる仕事”から “やるべき仕事”への発想転換を行う