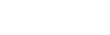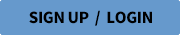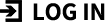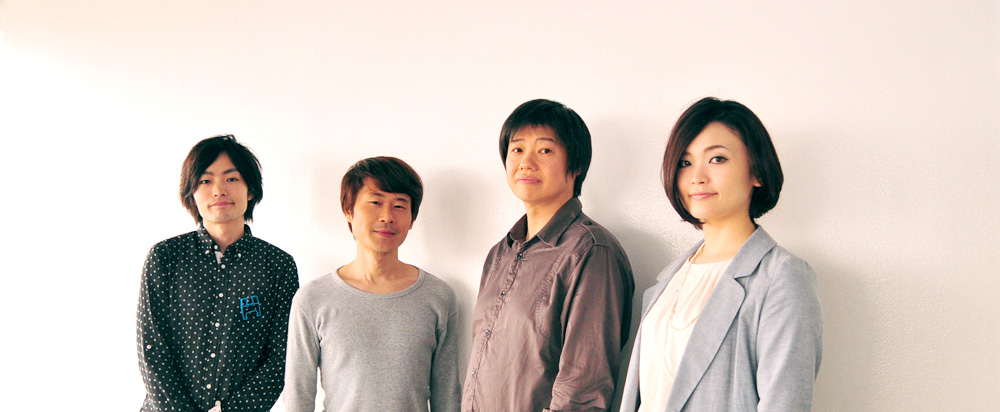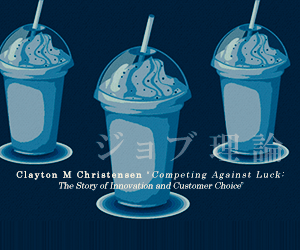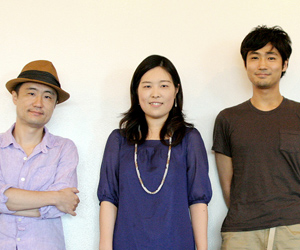取材・構成
OpenCU編集部「ものづくり」はもはやクリエイターだけのものではない。プロ・アマ問わず、様々なバックグラウンドを持った人々が一同に会し、用意された工具や機材を使って、ものづくりの世界に出会える場所が盛り上がっている。「ものづくりカフェ」と称されるの場でコミュニケーションやアイデアが生まれ、さらにソーシャルメディアを通じて作品が広まっていくような流れは、新鮮な経験だ。今回、はんだづけカフェから若山さん、小室さん、ガジェットカフェから吉弘さん、FabCafeから岩岡さんが集まり、特徴や魅力、今後の展望について座談会を繰り広げた。
まずは、それぞれのカフェの特徴の紹介から会は始まった。
秋葉原の旧中学校にある無料オープンスペース「はんだづけカフェ」
はんだづけカフェを運営するのは、株式会社スイッチサイエンス。電子工作に親しみのある人にとってなくてはならないモジュールの輸入・販売を行う通販会社だ。廃校を改修した秋葉原「3331 Arts Chiyoda」にあるはんだづけカフェは、いわゆるカフェとは異なる空間だそうだ。店長を務める株式会社スイッチサイエンスの若山雅弘氏はこのように語る。

はんだづけカフェ若山雅弘さん(左)、小室真紀さん
「運営しているスイッチサイエンスは、Arduinoというイタリアのマイコンボードなどの電子部品を扱っている通販のみの会社。そもそも、空いた会議室を開放したのが、はんだづけカフェの始まりなんです。ところが、はんだづけカフェにはスイッチサイエンスの商品は一切置いてないので、お金とは無縁の場所。それでも、秋葉原という地の利なのか一見さんがたくさん来てくださいます。
ここは“はんだや、テスターなど、初心者向けの機材が置いてあるので、自由にお使い下さい”という空間なんです。危険な機械もあるので、作業できるのは店員がいるときだけですが、店員がいない時間は見学はできます。カフェとはいえメニューがあるわけではないんです。
もともと、私はスイッチサイエンスに入る前、セガでゲームのプログラマーを20年以上やっていました。そこで、テレビの中だけでなく何か電子工作をしてみたいとは思っていましたが、電子回路はまったくわかりませんし、電源を作るなんて意味不明な状態。しかし、PCからプログラムを転送できるような基盤など便利で使いやすいものがどんどんできて、そんな折、縁があってスイッチサイエンスに入り、そのまま、はんだづけカフェの店長になりました」

2010年5月にオープンした、はんだづけカフェ。2011年には専用スペースを増設し、近日中にはもう1部屋オープン予定。はんだごての他にも、電源装置やオシロスコープ、カッテイングマシーンなど、多数の工具が備えられている。 http://handazukecafe.com
FabLabを源流とする渋谷のレーザーカッターカフェ「FabCafe」
「Fablication(ものづくり)」と「Fabulous(愉快な、素晴らしい)」の2つの意味が込められた“Fab”の精神を広く楽しく伝えるために生まれたFabCafe。店内では通常のカフェと同様に、お茶を楽しんだり、コ・ワーキングスペースとして活用することも可能だ。FabCafeのものづくりディレクターである岩岡孝太郎氏はその経歴を活かしてFabCafeに参画した。

FabCafe岩岡孝太郎さん
「私が慶應義塾大学の修士学生だった2010年5月に、FabLab Japanの設立が宣言され、翌年にはファブラボ鎌倉、ファブラボつくばが続々とオープン。そうしてFabLab Japanの活動が活発になっていく中で、ロフトワークとFabLab Japanの共同ワークショップが開催されたんです。
そのときに感じたのが、普段の仕事で交わることのない異分野のクリエイターが一緒に何かを作るときのエネルギーって、とてもいいな”と。このまま終わってしまうのはもったいないと思い、継続して活動できる空間を作りたいという話が持ち上がり、2012年の3月にクリエイティブディレクターの福田敏也さん、ロフトワークの諏訪・林のトータルプロデュースにより、FabCafeが誕生しました。
以前、建築意匠事務所で設計をしていたので、エンジニアリングに直接触れたのは大学院に入り直してから。FacCafeではレーザーカッターを始めとする機器を使ったサービス開発やプロダクト企画をしています」

FaxCafeの中心にはレーザーカッターが据えられており、iPhoneカバー、グリーティングカード、アクセサリーなど、多様なものづくりを体験できる。ドリンクやフードのメニューも充実しているため、通常のカフェ利用者も多い。無料で利用できるインターネット回線と電源も完備。 http://www.fabcafe.com/
常設の場所は持たないイベント中心型の「ガジェットカフェ」
最後に紹介するガジェットカフェは、いわゆる“カフェ”とは一線を画す。高円寺を中心に、クリエイターが出演する個性的なイベントが開催される時にだけオープンする、イベントスペースを提供している。ガジェットカフェを主催するのは、株式会社エンカフェの吉弘辰明氏。ガジェットカフェを始めた経緯について、次のように紹介した。
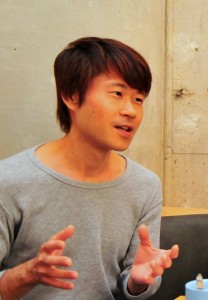
ガジェットカフェ吉弘辰明さん
「ガジェットカフェの源流は、「エンカフェ」というオンラインのエンジニア向けコミュニティです。なので今のスタイルは“オフ会”の発展系とでもいうか。ガジェットカフェは常設ではなく、イベントがある時だけコワーキングスペースを使ってオープンしています。
私はもともと、大学の材料工学科で金属材料について学んでいました。卒業後は、自動車部品メーカーに就職。“これは世界で誰もやっていない”という、クリエイティブな材料づくりがしたかったので、いろんな人とのネットワークやコミュニケーションの土壌が必要だと思っていました。そんなときに登場したのがmixi。『…これだ!』と思いましたね。
当時、ものづくりといえば製造業のイメージしかありませんでしたが、今は違います。表現っていうのは、機能を使うというより、感じるもの。それに気付かせてくれたのは、美大の卒業制作を見に行ったときです。そこには、ありとあらゆる表現があって、『ものづくりって、もっと幅広いものなんだ』と衝撃を受けました。それで、エンジニア限定のエンカフェではなく、ガジェットカフェを始めたんです」