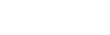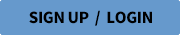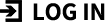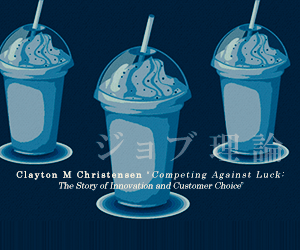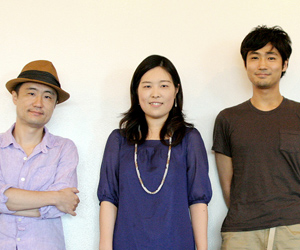グラフィックファシリテーションの心理学的な3つの効果
井口さんはグラフィックファシリテーターである前に、最終学歴でCalifornia School of Professional Psychologyの組織心理学修士を修める、心理学者でもある。続いて、実際に企業や組織でグラフィックファシリテーションを行った際にもたらされる心理的効果を聞いてみた。
「まずグラフィックファシリテーションは視覚が刺激されるファシリテーションです。人間の、特に目が見える人にとっては視覚の情報が一番大きいものです。しかも今自分が発言したことが、すぐに人の手によって形を与えられていく。さらにさまざまな色、フォントでそれらが描かれていくので、見るだけで脳のいろんな部位が刺激されます。それによってクリエイティブなアイデアが出るわけです」

CTWにて開催される「Visualize Your Process」というグラフィックファシリテーションを学ぶワークショップの模様。CTWでは2012年夏から「CREATIVE DELIVERY」と称した、アーティスティックなワークショップ群をリリース。写真やドローイング、CM振付師によるムーブメント等を使用したまったく新しいタイプのイノベーティブなワークショップ群となるそうだ。興味を持った方は、http://www.ctw.co.jpまで。
全員の意識を1枚の紙に集中させ、コミュニケーションを促進する
「次に、全員の意識を1枚の紙に集約することで、ポジティブで活発なコミュニケーションを誘発します。例えば、複数の人が話をして結論に至ろうとするとき、プリントを配ったりしてしまうとだめなんです。そうすると意識が自分のプリントのある手元に集中してしまって、全体がバラバラになってしまう。それがグラフィックファシリテーションの場合は、全員の意識が眼前の紙に集まるので、そこにひとつの共通言語のようなものが形成されるんです。これが視認性の向上と、高効率で物事をまとめ上げる作用をもたらします。おまけに、人間は体の状態が前、上を向いているだけで、不思議なほどに心も前向きになるんです」
「グラフィックファシリテーションでは、2時間前に言っていたこともずっとその場に残りながら進むから、過去と今と未来がそこに同時にあることになります。これによって、いわゆる“堂々巡り”が発生しません。これは人間の脳が自分の30秒前の発言を覚えるようにはできていないためなので、その30秒前の発言が紙に書き出される事自体に自然とコーチングの意味合いが生まれます。グラフィックファシリテーションを用いて“腑に落ちる”感覚を持ちながら進めていきます」
素晴らしいアイデアを誘発するための手法であるグラフィックファシリテーションが心理的な側面を多く持っていることには何ら不思議はないことだ。
ファシリテーションに求められるのは、客観性と主観性のバランス
先にグラフィックファシリテーションにおける、グラフィックの部分をテクニックとしてご紹介した。ここからはファシリテーションの部分を解説してみよう。
ファシリテーターは、いわゆる“進行役”。そのために必要なのは、客観性を備えた優れた主観でゴールへと導く能力だと井口さんは話す。
「全ての話を聴いてその中の流れを知る客観性と、例えば会議が難航しているとき、なぜ遭難しているのかを伝えるための航海地図を描いていく優れた主観性の両方が必要とされます。会議のいちメンバーである自分を思い出してみてください。案外、誰かが何かの発言をしているときに“長い”と思っていたり、“昼ごはん何たべよう?”などと、全然違うこと考えていたりするものです。いろんなことが頭の中を錯綜している。そのため会議では脱線と暴走が絶えず起こります。彼らは決して一本の道をきれいに走るものではない。ファシリテーターはそれに巻き込まれず、大きな流れを見られるようにならないといけません」
こればかりは経験がものを言うところかもしれない。しかし、何事も意識することから全てが始まる点では、心に留めておきたいところだ。
「さらにグラフィックファシリテーターで言えば、ペンの音が場をつくります。紙にペンで字を書くと、キュキュッと音がするでしょう。これが実は重要で、この音が常に響いている状態を保つのも仕事です。リアルタイムな場だからこそ、こんな小さなことも重要になってくるんです」
グラフィックファシリテーションは時間がきたら終わりにしなければいけない。そのリアルタイム性に全てがある。いわば時間制限を与えられた、アイデア作りをするアーティスト的な意味合いすらもそこにはある。
コミュニケーションプロセスデザインが求められている理由
井口さんは、“コミュニケーションプロセスデザイナー”という肩書きで、企業の組織運営をサポートする一貫でグラフィックファシリテーションを行なっている。彼女のセミナーはいつも満員御礼、そして企業からの需要はどんどん高まっている。
「組織心理学という学問が隆盛していった本場で得た体験や知恵をベースに、自分なりの哲学と方法論を生み出していこうとしています。」と井口さんはスタンスを語る。
最後に“コミュニケーションプロセスデザイナー”を名乗る理由についても聞いてみた。
「私の今のキャリアの全ては“人間ってなんだろう?”という知的興味が出発点になっています。そして、それを解明するには自分を解明するのがいちばんいいわけです。さらに、自分を解明することは、コミュニケーションを解明することと同義です。つまり私はコミュニケーションの研究者であり被験者なんです。そして、私たちはコミュニケーションの海に生きていて、ファシリテーションは、大雑把に言うと、人とのコミュニケーションを促進させるものです。
だから私は、自分がファシリテーターという肩書きよりも、コミュニケーションプロセスをデザインする人、である意味を好んで使っていますね。それに、プロセスを楽しむと、世界はもっともっと鮮明に、美しくなる確信が私にはあります。この仕事を通して、そうなってゆけたらいいなと考えていますね」
グラフィックデザイナー、プロダクトデザイナー、様々なデザイナーが世の中に存在する。それと同様に、人のコミュニケーションをつくるデザイナーが求められるのだ。
さて、もっと詳しく、より楽しく理解するためには、彼女の主催するワークショップに参加するのが一番だ。興味を持った方は以下から探してみてほしい。
井口奈保さん公式ページ:踊るシコウ
naho.iguchi[at]gmail.com

ワークショップ開催のご案内
思考のプロセスを可視化するグラフィックファシリテーション
ファシリテーションの基本理解を深めながら、会議やフォーラムなど、様々な人が集う場をファシリテートする場面で起こりうる状況に対して、グラフィックファシリテーションをどのように活用するか? その技術を習得する場を目指します。
- 2012年9月〜11月開催
- グラフィックファシリテーションのWhat, Why, Howをメルマガ形式でお伝えします。
- ワークショップイベントを月1回程度実施(WorkShopメンバーのみ参加可、開催地:渋谷・道玄坂Loftwork Labを予定) 2012年10月6日、11月3日、11月24日に開催。
- ◎第1回(10月6日10:00-13:00) 4,000円Graphic Facilitationでミーティングのネクストレベルプロジェクト進行の初期段階で特に重要な、コンセプトメーキングのためのアイディア出しから意思決定までを、GFで効果的に行なう方法を学びます。
チケット購入:https://tixee.tv/event/detail/eventId/441
(Tixeeにてオンライン決済をお願いします) - 詳しくは、ワークショップトップページ「思考を整理するグラフィック・ファシリテーション」の「Learn More」からご確認ください。