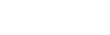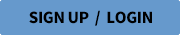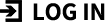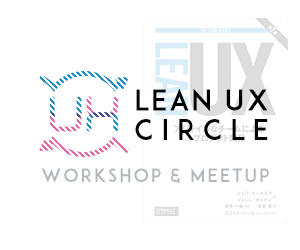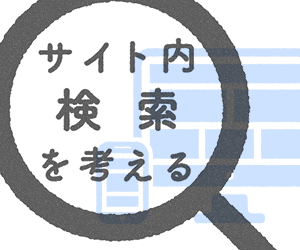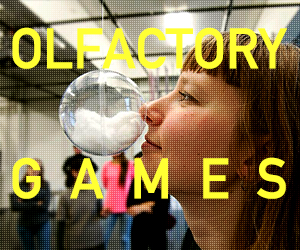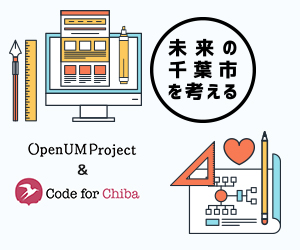ヒットを生み出すのは、本能をわし掴みにする発想だ
タナカさんが手がける制作物は、人間の“ニッチな欲望”にダイレクトに訴えかけるコンセプトが目立つ。こうしたクリエイティビティにはどんな哲学があるのだろうか?
「自分を含め、みんな本当はシンプルなんだって思いますね。どんな情報でもちゃんと届くシンプルな伝え方というものがあって、それをちゃんとすれば受け取ってくれる、って思うんです。つまり、どんな人でも、ある部分子供の心を持っていると思うんですよ。本能で“欲しい”とか“楽しい”と思っていることに対しては神経を集中するし、アドレナリンが出てしまう。制作物には、、バカな自分が感じているシンプルな欲求、あるいは感動と、伝えなければいけない情報をマッシュアップしようと思っていますね」
バカバカしいと思いながらもめりこんでしまうような感覚、それこそタナカさんのクリエイティビティの真骨頂と言えるものだ。
「感情とか衝動とか、全てはきちっと理由がある。自分が“これ面白いな”とか“超萌える”とか、“なんでツンデレはいいのか?”なんて思ったときに、それを受け取った自分を理論立てて考えてみるんです」とタナカさん。自分が素直に受け取った情報をそのままにせずに、それを掘り下げて自分のストックにしてゆく。そうすることで、素直に受け取れる情報を自分で作り出せるようになるという。
そしてそういった感覚はインターフェースのデザインにも生かされているという。
「たとえば、Twitterと連動した企画があって、ツイートしてくれた人に何かのプレゼントがあるとする。こうした場合も、ツイートボタンのすぐ近くにプレゼントの応募情報があったほうがいい。人は自分が得することと、それに大してアクションを起こすものとの距離が短い方がいいんです。大勢での呑み会で食卓の上に大好物があったとき、手が出せる範囲ってあるわけですね。あの距離感と一緒なんですよ」
「ネットだと新しい技術がどんどん出てくるので、ついつい使いたくなるけど、それで複雑になってしまうとやっぱりうまくいかないと思ってます。それと情報についても、なんでもかんでも盛り込んでいこうとすると、伝えたいことがぼんやりしてしまって伝わらなくなってしまいます。伝えないといけない事をシンプルにまとめていって、それを技術でダイレクトに伝える感じですかね」
思えば“キスしたくなるくちびるコンテスト I want you”はデザイン的にも技術的にも極めてシンプルだ。でも、それにユーザーは釘付けとなる。大切なのは、シンプルな熱や欲求を、どれだけ失わせずに伝えきれるかだ。
オリジナリティ溢れる発想は、完全なオリジナルを諦めることから始まる?

「Panasonic | PLAY!! NIGHT COLOR -パートナー。Panasonic-」 2010年7月 ディレクション、デザイン、FLASH実装、HTML Client:パナソニック Agency:株式会社 博報堂 Production:株式会社 東北新社、株式会社 ピクルス、メディアパルサー
【サイトの解説】
トップ画面(左)では、コーネリアスのBGMをバックに、家電をクリックことでサウンドが鳴り、演奏できる仕組みを展開。また、iPhoneアプリやQRコードを介して、ユーザーのTwitterアイコンが頭になった人物が体操をするAR(拡張現実)を楽しむことができる。また、体操はYotube動画としてアップでき、この仕組みを用いた応募キャンペーンが展開された。(現在は募集は終了)
クリエイターの誰もがオリジナルという存在に憧れる。タナカさんの制作物も、どれもオリジナリティに溢れている。しかし本人はオリジナルそのものを目指しているわけではないという。
「“オリジナル”と言われているもののほとんどは、何かのマッシュアップだと思うんです。Webの世界でも、基本的にはリアルをどう置換したかということに過ぎない。最初にGoogleがヒットしたのも、単なる検索エンジンではなくて、被リンクというランキング検索だったというのが大きい。これって、検索に“ヒットチャート”という概念を持ち込んだと思ってます。グルーポン系サービスなんてのも、分かりやすく言うとスーパーの7時過ぎの半額セールをWeb上で開催している。全てはリアルの感覚の置換なんですよね」
Webではついつい見せ方に騙されがちだが、元をたどればそれらは全てリアルの世界をメタファーとして組み合わせ、Webのインターフェースやサービスとして作り替えているに過ぎない。そしてリアルの世界でも真のオリジナルは存在しない。文化ですらも、歴史の中で生まれた創造物を組み合わせて生まれているのだ。
「真似されるというのはすごいことだって思うんです。自分が作ったものが真似されるというのは、それだけ創造性が高いとも言えますからね。僕も過去やった企画を色んなところで真似されてますけど、そう思えば誇りに思えます(笑)。それに他の人がやった施策なんかも参考にしてます。要はそのまま持ってくるんじゃなくて、“この使い方は思いつかなかったな〜”って思ってもらえるかどうかだと思うんですよ」
タナカさんはこう続ける。
「真似されることは、制作物に対する最大の賛辞。逆に言えば、誰にも真似されないものは、すでに価値がそこで閉じてしまっているもの、つまり“大したことないもの”となるじゃないですか。“真似をされないもの”と、“真似できないもの”というのは全く違うと思うんです」
完全なオリジナリティの幻想を目指すのではなく、いろんなものを真似して応用して、誰にも真似できない組み合わせを発想すること。それがオリジナリティ溢れるクリエイティブと言えるもの
次回はタナカさんの30歳からの業界デビューをお届けします。乞うご期待!